センターの役割
1. 産業界に役立つ研究開発人材の育成
産学官連携による研究活動を通して、学術的シーズと産業界・利用者ニーズに精通した人材を育成します。
インシデントに対応できる専門家を、関係機関への出向などを通じて育成します。
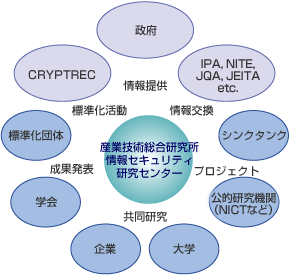
2. 裏付けのあるセキュリティ情報の発信源
高いレベルの研究成果を出し続けることで、専門研究により裏付けられた信頼できる情報の発信地としての役割を果たします。
3. 重要インフラ等の安全性評価
公的研究機関として、現行の評価手法よりもさらに高品質な新しい手法の研究や、最先端の手法を用いた重要インフラの評価を行います。脆弱性を発見した場合には、情報処理推進機構(IPA)等の適切な伝達ルートを通して、関係者へ脆弱性情報及び対処法を周知します。
4. 他分野の専門家との連携による相乗効果
1.情報セキュリティ研究センター内での連携
基盤技術、ソフト、ハード、ネットワーク等の技術を総動員した新技術の提案を行います。
2.研究所内の他分野との連携
グリッドコンピューティング、セマンティックWeb、オープンソース、光通信技術、システム検証技術など、情報セキュリティが重要な位置を占める分野の研究者とも連携して研究を行います。
3.外部研究組織との連携
大学、公的研究所、民間企業等と研究プロジェクトを立ち上げ、日本の情報セキュリティ分野のレベルアップ、新産業の創出を目指します。
※すでに2004〜2006年度、科学技術振興調整費のプロジェクト「セキュリティ情報の分析と共有システムの開発」(企業、大学、IPA、NICT等が参加)へ情報セキュリティ研究センターの研究員が3名参加しています。)
4. 関連団体との連携
内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)、情報処理推進機構(IPA)、製品評価技術基盤機構(NITE)、日本品質保証機構(JQA)、電子情報技術産業協会(JEITA)などの関連団体と連携し、最先端の研究に基づく情報の提供、問題の解析、対処法の提案などを行います。
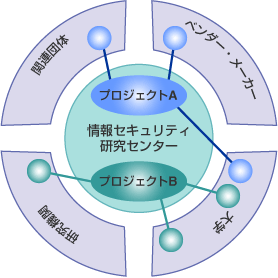

![[HTTP Mutual Access Authentication]](/files/special/MutualAuth/index-en/mutual.png)
![[Fail-Safe C]](/files/project/FailSafeC-ja/FSC-logo.png)
![[暗号モジュールの物理解析攻撃]](/special/SASEBO/SASEBO_banner.png)
![[LR-AKE]](/files/project/LRAKE-en/renew8.gif)
![[QR-JAM]](/files/project/index-ja/qr-jam-150.jpg)